
この映画、観たことあるけど、正直良さが分からなかったよ…

そう感じる人も結構いるだろうね
はじめに
「東京物語」は海外からも高く評価されていて、不朽の名作と言われたりしますよね。でもいまいち良さが分からない…という人も結構いるんじゃないでしょうか?
もちろん、感じ方はひとそれぞれで不正解はありません。けど、もう少しこの映画を理解したり、楽しんだりしたいと思っているあなたに、ぜひ知ってほしい視点があります。それは当時の人たちの価値観と家族関係です。
私自身、洋邦問わずヒューマンドラマを数多く観てきましたが「東京物語」はトップ3に入るような、心に残る映画だと思います。この解説をふまえてもう一度観ることで、きっとあなたの心にもじんわりと残っていくでしょう!
当時の日本社会と家族の在り方
この映画は、1953年(昭和28年)の公開で、時代設定も同じ時代のようです。戦争が終わって8年後ですね。高度経済成長期に突入していく時期でもあります。
団塊の世代(昭和22~24年生まれ)が遂に後期高齢者となりましたが、この映画、まさに団塊の世代が子どもだった時代の話です。そう聞くと、ちょっと身近に感じられませんか?
当時、日本はすごい勢いで発展していたため、田舎から都会へ出ていく人が激増していました。

この映画でも、長男と長女は東京、三男は大阪に暮らしてるんだよね

そうそう、末っ子以外はみんな尾道を出て行ったんだ
そして都会で出世し両親を喜ばせることが“成功”の代名詞のようなものでした。ですが輝かしい業績を上げられるのはわずか一握り…これは今も昔も変わりませんね。
この映画は当時の日本社会の中で葛藤しながら生きた普通の家族の物語です(といっても多少裕福な家庭のようですが)。そこにある期待と幻滅、見栄と本音、様々な葛藤が丁寧に描かれています。
出世の夢と厳しい現実
長男の幸一は“東京で医者”として働いています。一見素晴らしい成功を収めているように聞こえますが、現実は東京の外れでこじんまりとやっている町医者です。急患があれば家族との時間を犠牲にしてでも往診に行かなければやっていけないような状況なのです。
母親とみは母性的で穏やかな性格ですが、夫の周吉と二人だけになった際、幸一の住まいについて「もっと賑やかなとこか思うとった」とぼそっとこぼします。周吉は「そうもいかんのじゃろう」とたしなめますが、彼自身も幻滅を感じたのが本音でしょう。

長男、頑張ってるんだけどねぇ…。まあ親としても期待したくなるのかな。

なにげにリアルな描写だよね…
親孝行をしたくても…
最初は両親の上京を歓迎していた長女の志げも、稼業の忙しさには敵いません。のんびりと滞在を続ける両親の様子に対し「お父さんお母さん、いつまで東京にいるのかしら」と罪悪感と不満の入り混じった愚痴をこぼします。志げは、兄弟の中では一番感情的で自己中心的な性格として描かれています。しかし一番等身大の感覚の持ち主であり、この言葉は、その場にいた兄弟たちの本音を代弁しているだけとも言えるでしょう。みな両親を思う気持ちはやまやまですが、自分たちの生活を考えない訳にはいかないのです。
ヒロインは良心の擬人化?
ちなみに、ここまで肝心のヒロイン紀子(戦死した次男の妻)について触れていませんでした。というのも、紀子は良い人(完璧)過ぎて人間的なリアリティに欠ける感じがあるんです。しかし、逆に言うと他の人たちの良心や罪悪感を、ギュッとまとめて擬人化しているようにも見えます。紀子の存在によって生々しい現実が“物語”に仕立てられているのかもしれません。

紀子さんみたいな理想的な存在がいると救われるよね

ずっと現実と向き合い続けるのは心苦しいからね
まとめ
都会で一旗揚げ、親を喜ばせることが子どもたちの夢であり、また親もそのような夢を託したことでしょう。しかし現実は厳しく、子どもたちは“自分の生活”を優先せざるを得ません。そのジレンマは、当時を生きていた多くの人の心の内に、無意識に共有されていたのではないかと思われます。
映画は激的な展開もなく、淡々と進んでいくため、“つまらない”という評価も一定あります。確かにそう感じる人もたくさんいるだろうな~と私も思います笑
しかし、穏やかな映像とは裏腹に、登場人物の心のうちに思いを巡らせるとき、その感情がひしひしと伝わってくるように感じられます。お伝えした視点をふまえつつ、もう一度観てみてください。きっと心にじんわりと響きますよ!
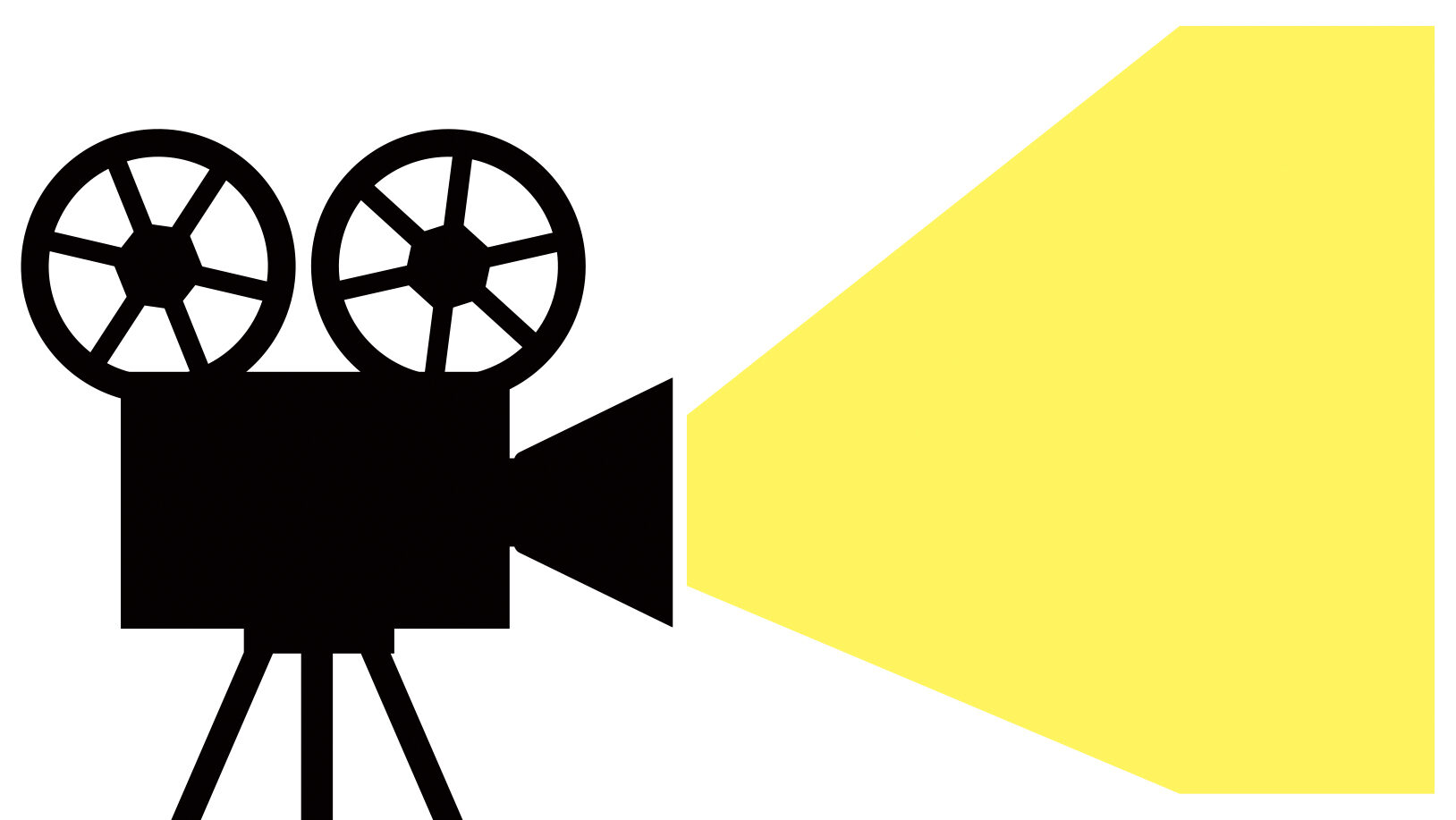

コメント